※外部サイトへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれている場合があり、購入や会員登録の成約などから、当サイトが収益化を行うことがあります。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
「多読」という言葉もありますが、フランス語力を高めるには"単に読めば良い"わけではありません。
私は、仕事上で英語の資料を読んだりしますが、「内容がわかれば良い」レベルなので、精読しているわけではありません。
学習向けに英語・仏語の文章を読む時に、私がとくに心がけていることを紹介します。
フランス語を和訳しない
これはもう、日本の英語教育のよろしくなかったところだと思いますが(今はどうなのか知りません)、何でもかんでも和訳するのはNGです。
「辞書を引いて単語の意味を知る」程度に留めます。
語学を身につけるには、「その言語で考えられるようになる」脳を作ることです。日本語で話す私達は、言葉を発しない時も頭の中は日本語になっています。そこに、英語なら英語の回路、仏語なら仏語の回路を作るのです。(※私のイメージです)
私自身、英語を話しているときは頭の中は英語で考えていますし、フランス語を話す時はもちろんフランス語で考えています。
せっかく語学を身につけようとしているのに和訳することは、その言語の回路を離れてしまう行為になり、新しい言語の回路は発達しません。
それに、「訳す」ことは、外国語を話せるようになることとは別の技術です。
和訳とは、近い意味を持つもっとも適切な日本語を、即座に自分の脳の引き出しから探し出して文章を構築するという、まったく違う作業になります。
たとえば、翻訳者や通訳者はそういう技術を磨くわけです。私は英語もフランス語も「和訳」は得意ではありませんが、それはその言語を理解できないこととは異なります。
フランス語なら、フランス語の語順のまま即座に理解できる様になるのが目標なので、わざわざ和訳を求められている場合を除いては、和訳は避けるのが鉄則です。
とりあえず最後まで読む
私が読んでいるle Figaroのオンライン記事は、大体500語~600語程度のものになります。
単語を調べないとまったくわからない場合は、この半分位のものから始めてもよいと思います。
とりあえずは最後まで読み、知っている単語だけでニュースの内容をイメージをした上で、単語を調べていきます。
初めから単語を調べながらですと、やはり途切れ途切れになります。
やってみるとわかりますが、単語を調べながらでは文章が頭に入りにくいです。私はわからない単語に印をつけ、一通り読んだ後に単語をチェックをしています。
フランス語の文章中には、単語の意味を日本語で書かない
私は「Le Figaro」の記事をプリントアウトして読んでいますが、単語の日本語の意味はそこには書き込みません。
Le Figaroの記事をプリントアウトしたもの。わからない単語は色ペンで印だけ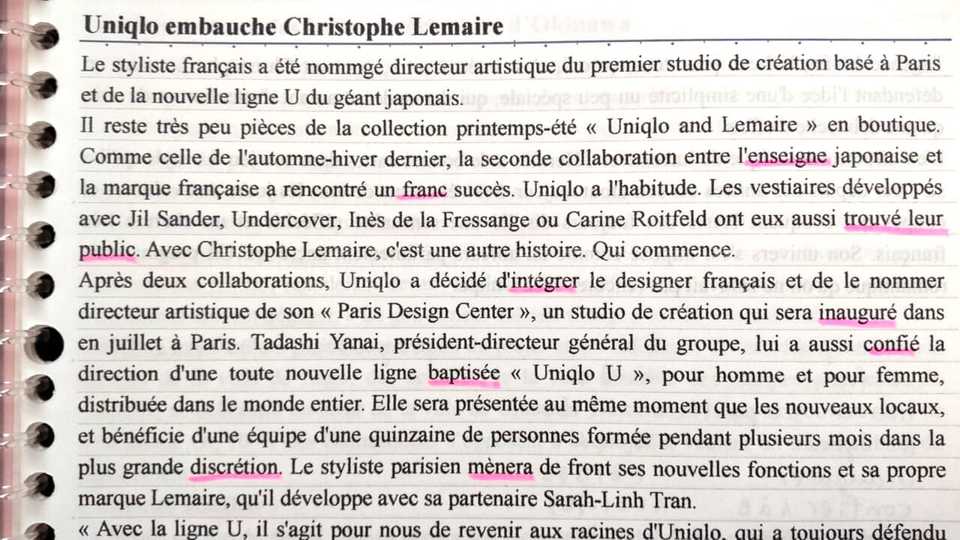
これは後で読み返す時のためですが、日本語で単語の意味を書き込んでしまうと、意識しないようにしてもどうしてもそちらに目が行ってしまい、後で読むときに結局憶えたかった仏単語を見なくなってしまいます。
単語は別の場所にリストを作り、その文章を後で読み返すときには目に入らないようにするのが、フランス語を身につけるためのコツです。
もちろんフランス語で書き込むことは良いと思います。
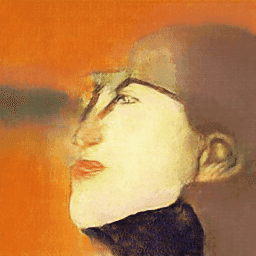
私の場合、略称(CSG、CSAなど)や略語(Ndlrなど)のみにつき、その正式名称を文章内に書き込んでいます。
略称や略語はフランスで暮らしていないと知らない場合が多く、大抵は辞書には載っていませんので、googleで調べることが多いです。
ただ、略称の場合はわからなくても「何かの機関名かな」程度で流してしまうことも普通によくあります(フランス国内の団体の通称がわからなくても、読解力UPの妨げにはなりません)。
単語を調べ終わったら、通しで2回程度読む
フランス語の語順のままで理解できる様に、わからない単語もチェックし終えたら、何度かその文章を読み直します。
単語は1回調べただけでは憶えていないことも普通にあり、何度もリストを見返すこともあります。
ただ、これはテストではないので、流れが90%程度わかればOK!
調べた単語がまたわからなかったら、その都度チェックすればいいのです(エクセルで単語リストを作っていると、その単語が以前も出てきたかどうかが把握しやすい)。
音読でももちろんOKです。耳から音を入れることができるので、より仏語回路が発達します。
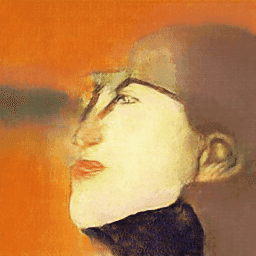
私は高校生の時は、英作文は読みながら書いていました。やはり成績は悪くなかったですよ!
忘却曲線のグラフが下がってくる1週間後・1か月後にまた読み返せば、記憶定着もUPです。
まとめ
千里の道も一歩から。語学には根気と地道さが必要です。
幸い、現代はインターネットのお陰でオンライン記事もいくらでも見つかりますし、教材には事欠きません。
私が今回紹介している「Le Figaro」ではなく、「Le Monde」「NHK WORLD」などでももちろん良いですね。

今回は私個人のやり方ではありますが、1つの参考になりましたら幸いです。

 Le Figaro](/static/a053401daa43a17a604c49de890d0e94/d9199/le-figaro-01.png)