※外部サイトへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれている場合があり、購入や会員登録の成約などから、当サイトが収益化を行うことがあります。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。
2022年12月現在Amazonプライムで観られる「パリに見出されたピアニスト」を鑑賞。
Amazonでの評価はまずまずなのですが、いやこれ、設定と脚本がかなりひどい。と思った。
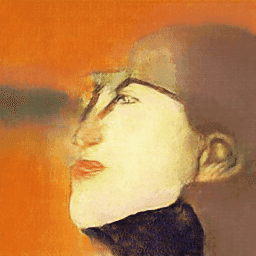
誰ですか、この脚本を書いたのは・・・
実際のところ、監督が脚本も書いているとか。久々の、フランス映画の駄作に出会いました・・・
以下、ネタバレ・残念な感想を含みます。この映画を好きな方、楽しんで映画を観たい方はここでお帰りください。
だめなところ:ピアノコンクールの設定
私はそこまでのコアファンではありませんが、国内外の有名な国際ピアノコンクールをライブで観たりはする、かなり軽めのクラシックファンです。
何なら、某国際ピアノコンクールのボランティアスタッフ(コンテスタントのお世話系)の経験も少なからずあります。
というわけで、コンクールの演出については違和感しかなかったです。
ダメその1. ファイナリスト以外はオケと協奏しない
国際的なピアノコンクールでは、オーケストラとの協奏は、ファイナリストだけに与えられる権利であり栄誉です。
1次予選、2次予選、3次予選と次々の激しい振り落としを勝ち進み、100人以上のコンテスタントの中からオーケストラとの協奏曲を披露できるはたったの6~10人。(大会により人数は異なる)
しかも、本番の前日までには必ずリハーサルがあります。
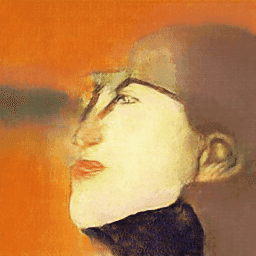
もしかしたら映画の中でもそういった設定があった上で、リハ風景などは省略されているだけなのかもしれませんが・・・
でも、練習風景ですら、ピアノのレッスンだけで「準備は万全ね!」的なことも言っていたので、どうしてもコンクールの場面はいきなりはじめてのオケ合わせだったように見えてしまう。
オケと1回も合わせずにぶっつけ本番なんて、絶対に!ぜっっったいに!あり得ません。
ダメその2. 集合時間に来ないと普通は失格
コンクールの際、コンテスタントは本番時間の1時間~45分前に集合することが求められます。その後、控え室で練習や着替えをし、自分の出番の5分前には舞台袖で待機。
舞台袖では、舞台監督が秒単位で厳密に時間を管理し、コンテスタントが舞台表に出てくるタイミングをコントロールします。
本作では、出場者である主人公は、名前を呼ばれた時にも会場にまだいない。そうこうしているうちに、結婚式に花嫁を奪いにきた男性の如く彼がドアをバタンと開けて会場に登場し、演奏・・・
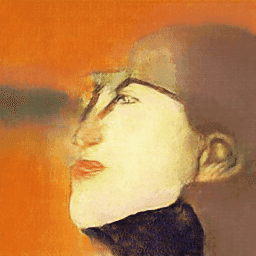
「ドラマと言われればドラマ」なんですが、裏側を知っているから無駄におかしく感じてしまう・・・
それでいて、個人のコンクールにおいて代役なんてあり得ません。それとも、学校対抗戦か何かだったのでしょうか?
いや、劇中で「国際ピアノコンクール」と言っているから、それはないよな・・・
ダメその3. 補欠の扱い
音楽院のレッスンで、オケと一緒に練習しているピアノ科の学生。「コンクールには俺が出る」と主人公に宣言し、対抗意識を燃やします。
個人で国際コンクールに参加する場合、劇中のように学校で一人という制限があるのもやや不思議ですが、補欠は出場者の誰かが自体した場合に、大会の数週間前までに補欠者に通知され、参加の意思が確認されます(準備や渡航の必要がありますしね)。
当日、その本番のその瞬間に、いきなり補欠が登場とは・・・いやいやいやいやいや・・・
やはり、「学校対抗戦」という位置づけなのでしょうか?
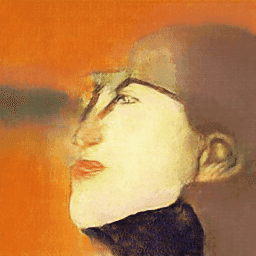
実際のところ、私のクラシックオタク度が低すぎるだけで、1次からいきなりオケ・当日代役OKの国際ピアノコンクールが存在するのかもしれません。あったら教えてください。
だめなところ:脚本がひどい
ダメその4. 怪我はなんだったの?
劇中、ピアノの練習をしすぎた主人公は腱鞘炎を負い、医師にピアノを弾くことを禁止されます。
主人公は「なんだよ!ちくしょう!気にしねぇ!」などと言い、練習再開。その後・・・問題なく練習は進み、準備OK状態に。怪我はなかった存在にされていました。
あの腱鞘炎のシーンは一体何のためにあったのか・・・
考察
以下は完全に、私の個人的な想像です。監督や俳優のインタビュー記事などは読んでいませんので、事実と違う可能性があります。
私としては、この監督兼脚本家さんは、駅ピアノを目にしてストーリーを思いついただけなのでは、と感じました。
そして、この監督兼脚本家さんは、
- クラシック世界の知識はない
- でも、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番は好き
- フランスの下流階級の青年の成長物語にしようと思った
のではないかと拝察。
元の設定自体は悪くない
お金持ちばかりの音大の責任者が、駅ピアノを弾いている貧乏な青年に才能を見出し、自分の進退をもかけてその青年に最高の指導を提供してコンクールに出す。
その設定自体は別に悪くないとは思います。というより、むしろありがちです。ありがちすぎて、展開が読めるほどです。
ただ、とにかくコンクールの演出が雑。クラッシックのファンでもない制作者のイメージだけで、一切の取材もしていないのでは・・・
それでいて、よくもこのコンクール演出で、パリ音楽院が名前を使うことをOKしたなと。音大生が、なかんずくピアノ科の学生がこの映画を見たら、もっと違和感が大きいのでは?
青春ファンタジーとして見ればOK?
設定を現実的な部分と合わせるとものすごく無理がありますが、これが「青春ファンタジー」と思って見れば、アリなのかもしれません。
それと、やはりいいのは音楽そのものと、ピアノの先生役のクリスティン・スコット・トーマス。フランス語が流暢すぎて惚れますw
とにかく、コンクールの裏側を知っているだけに、私にとっては違和感ばかりが気になってしまった映画でした。
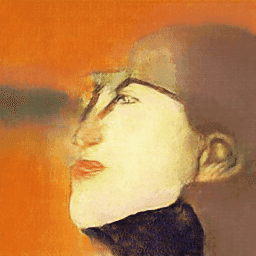
ちなみに、ピアノコンクールのフィクションで言えば、恩田陸「蜂蜜と遠雷」は緻密な取材を元に書かれた傑作です(それでも、裏方としては多少のツッコミ所はありますが)。
コンクールの演出がなければ、よくありがちな青春成長映画。気楽に観る分にはいいのかも?

![パリに見出されたピアニスト [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SXQrZyt4L._SL500_.jpg)